
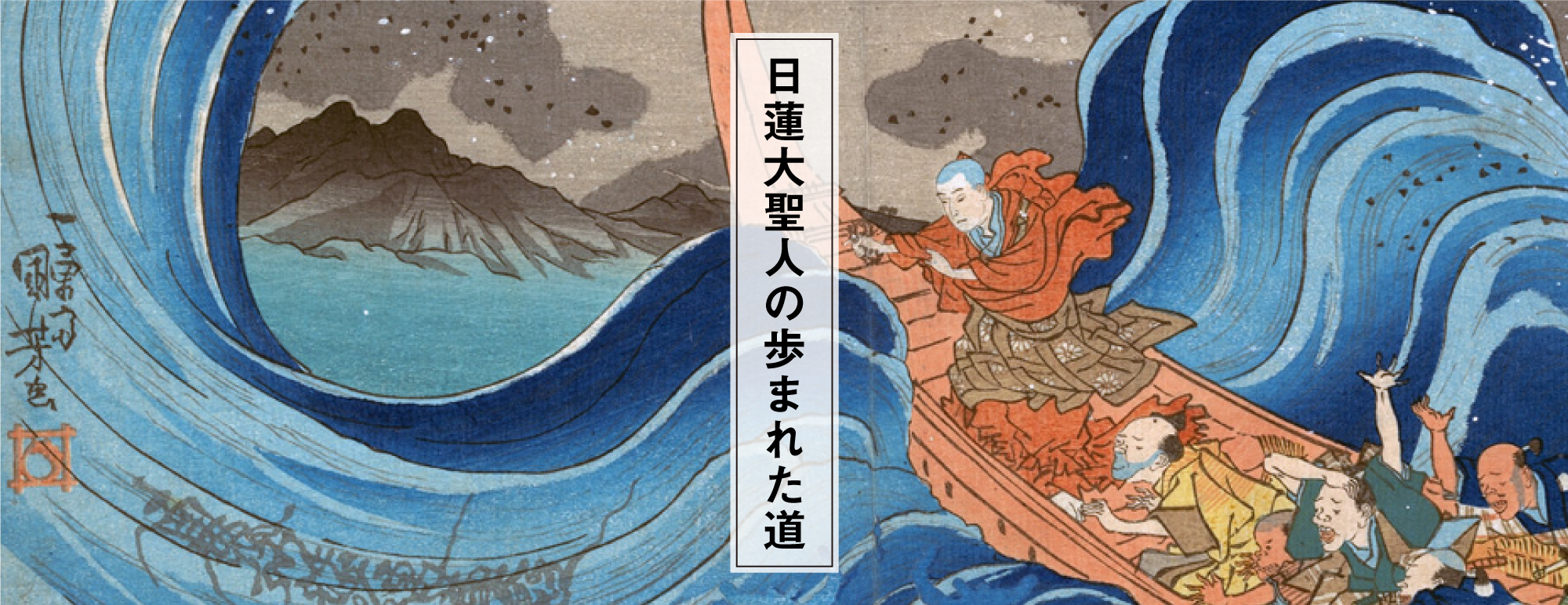
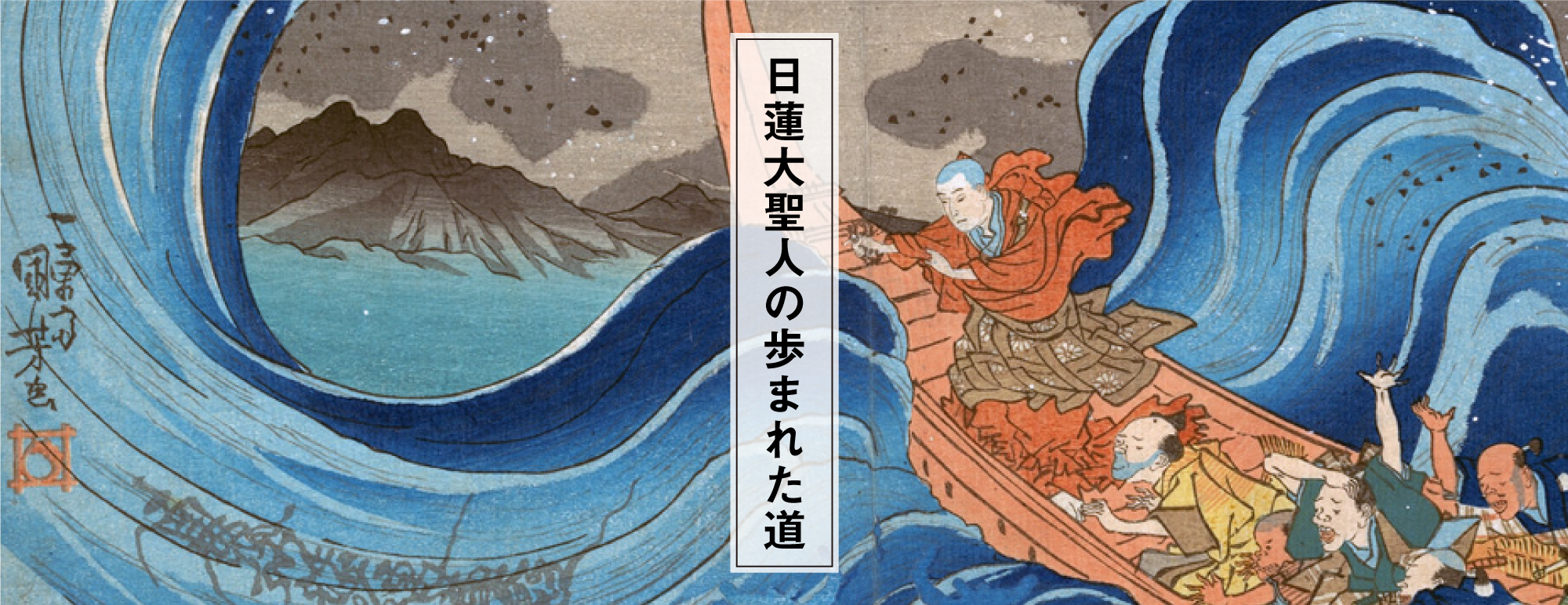
上宮太子と申せし人、漢土より始て佛法渡させ給て、其より以来于今七百余年の間、一切経並に法華経はひろまらせ給て、上一人より下万民に至まで、心あらむ人は法華経を一部、或は一巻、或は一品持て或は父母の孝養とす
松野殿後家尼御前御返事(まつのどのごけあまごぜんごへんじ)

いよいよ諸山巡りも終わりに近付いた蓮長(れんちょう)は、河内にある磯長の叡福寺を訪れました。
叡福寺は聖徳太子が推古二十八(六二〇)年に、自らこの地を墓所と定められたとされる由緒ある寺院です。その翌年には太子のご生母である穴穂部間人皇后が崩御され、この地に埋葬されました。そして推古三十(六二二)年、太子のお妃である膳部菩岐々美郎女、そして翌日には後を追うように太子ご自身が相次いで薨去され、共にこの地に追葬されたといわれています。
推古天皇は太子の没後にその菩提を弔わんと願い、ここに御廟をお守りするための僧坊十姻を建立します。それが当寺の始まりであるとされています。更にその後の神亀元(七二四)年には、聖武天皇の勅願によって東院(転法輪寺)、西院(叡福寺)などが建立され、やがて現在の叡福寺に至る伽藍が整えられました。
蓮長はこの叡福寺の太子廟に詣で、そこで七日間の参籠に入ったといわれています。以前に和泉の四天王寺を訪れたことをお話ししましたが、他にも法隆寺夢殿への参詣、そしてこの叡福寺での御廟参と、折にふれ太子縁の寺院を歴訪する蓮長の行いを見れば、やはり蓮長にとって太子は特別な存在であったことが伺えます。それを思えば、この日本国に佛法を弘めた大恩人たる聖徳太子の尊霊に額づき、二十年もの間修め続けた学問の成果をご報告し、そしてその研鑽によって導き出された答えとして、今胸中にはっきりと浮かぶ己が使命への決意を、太子にお誓い申し上げたに違いありません。

やがて七日目の夜を迎え、その行も満ちようとする中で蓮長は夜を通して法華経を読誦していました。すると不思議なことに、誰一人いなかった筈の墓前に眩く輝く人の姿が現れます。蓮長が目をこらしてその姿を見れば、なんとそこに現れたお方は、聖徳太子その人であったのです。
衣冠を正したお姿の太子は、そっと蓮長の前に立たれました。蓮長は驚きながらもそのお顔を拝すると、満面の笑みをたたえておられます。それはまるで、太子ご自身が大切にされた法華経を弘めんと決意する蓮長の思いを、殊の外お喜びになっているような優しい微笑みでした。
イラスト 小川けんいち

宗会議員
霊断院教務部長
千葉県顕本寺住職
バイクをこよなく愛するイケメン先生